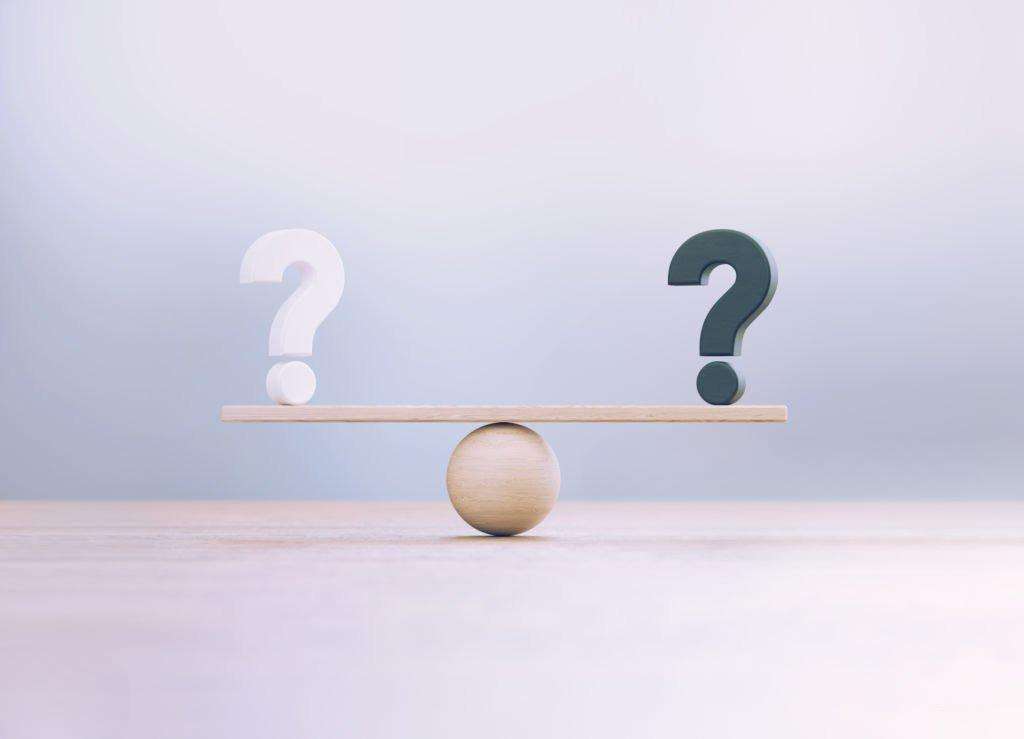大規模改修プロジェクトにおいて、元請け担当者様の肩には常に大きな責任がのしかかります。特に防水工事は、建物全体の寿命と資産価値を直接左右する重要な工程です。もし、ここで施工不良が発生すれば、数年後に漏水が再発し、施主様の信用を一気に失うことになりかねません。
「防水は、漏れたら全てが終わりだ」
そんなプレッシャーの中で、協力会社となる防水業者を選定するのは非常に神経を使う業務です。 例えば、コストを最優先し、最も安い見積もりを提示した業者に発注したとします。しかし、その業者が現場管理をおろそかにし、必要な下地処理を省いていたとしたらどうでしょうか。竣工直後は綺麗に見えても、数年後に必ず不具合が発生します。
あるいは、下請けへの丸投げ体質で、現場の職人にまで指示が徹底されていないケース。天候不良や他工種との兼ね合いで急な工程変更が必要になった際、迅速な対応ができず、プロジェクト全体の工期遅延を招くかもしれません。
そうなった時、最終的な責任を問われるのは、その業者を選定した元請け担当者様ご自身です。 大規模改修における防水業者の選定は、単なる「コスト削減」の業務ではありません。それは、施主様からの信頼、そして自社の評価を守るための、最も重要な「リスク管理」業務と言えます。
この記事では、そうした重圧や不安を抱える元請け担当者様に向けて、後悔しない業者選定のために本当に確認すべきポイントを、専門的な視点から解説していきます。
■まずは押さえたい、防水業者選定の「一般的な3つの基準」

多くの元請け担当者様が、防水業者を選定する際に比較検討する一般的な基準が3つあります。まずはこれらの基本的な項目と、それだけで判断する危険性について整理します。
・1. 価格(見積もり金額)
最も分かりやすい比較基準です。プロジェクト全体の予算を管理する上で、コストは非常に重要です。複数の業者から相見積もりを取り、金額を比較することは基本中の基本です。
ただし、注意すべきは「なぜその金額なのか」という内訳です。同じ工法でも業者によって金額が異なるのは、下地処理の範囲、使用する材料のグレード、あるいは現場管理の体制が違うからです。単に「一式」と記載された見積もりや、極端に安い見積もりは、必要な工程が省略されているか、後から追加費用を請求されるリスクをはらんでいます。
・2. 施工実績
過去にどれだけの規模の、どのような建物の防水改修を手掛けてきたかという実績は、業者の経験値を示す指標となります。特に、今回担当する現場と類似の施工実績(例:同規模のマンション、複雑な形状の屋上など)があれば、安心材料の一つとなります。
しかし、実績件数が多いからといって、現在の施工品質が担保されるとは限りません。重要なのは、その実績を「どのような施工体制で実現してきたか」です。
・3. 保証内容
施工後の保証年数や保証範囲も重要な選定基準です。「10年保証」といった長期保証は魅力的に映ります。 ここで確認すべきは、「メーカー保証」なのか「施工業者の自社保証」なのか、あるいはその両方なのか、という点です。また、万が一漏水が発生した場合、どのような手順で、どれくらい迅速に対応してくれるのか、免責事項は何か、といった具体的な内容まで確認しなければ、いざという時に機能しない可能性もあります。
■見積書には表れない「現場対応力」。ベテラン元請けが重視する3つの視点

価格、実績、保証。これらはあくまでも契約前の「書類上」で比較できる情報です。しかし、大規模改修の現場は生き物であり、想定外の事態はつきものです。ベテランの元請け担当者は、書類上の数字以上に「現場対応力」を重視します。
・1. 天候や他工種への柔軟な調整力
防水工事は天候に大きく左右されます。雨天が続けば当然、工程は遅れます。問題は、その遅れをどのようにリカバリーするかです。天候の合間を縫って効率的に作業を進める段取り力や、他工種(塗装、足場など)との工程調整をスムーズに行うコミュニケーション能力は不可欠です。こうした調整力がないと、防水工事がボトルネックとなり、全体の工期に影響を与えます。
・2. 想定外の事態への「報告・相談・提案」のスピード
既存の防水層を撤去してみたら、想定以上に下地の劣化が激しかった、ということは改修工事では日常茶飯事です。この時、「勝手に簡易補修して進めてしまう」業者が最も危険です。
信頼できる業者は、必ずその時点で元請け担当者様に状況を即座に報告し、複数の対応策(例:このまま進めるリスク、最適な下地処理の方法と追加コスト・工期)を具体的に提案します。この「報・相・提」のスピードと質が、最終的な品質と元請けの安心感を左右します。
・3. 現場での安全管理と整理整頓の徹底度
現場の安全管理体制や、材料置き場の整理整頓具合は、その業者の「仕事の質」を如実に反映します。安全への配慮が欠けている現場は、必ず施工品質にも緩みが出ます。また、整理整頓ができていないと、材料の取り違えや不要な事故を誘発します。日々の現場の様子は、元請けとして自社の信用を守る上でも厳しくチェックすべきポイントです。
■大規模改修で絶対に避けたい、防水業者選定の「最悪の失敗」3パターン

現場対応力のない業者を選んでしまうと、元請け担当者様の不安は的中し、最悪の事態を招くことさえあります。ここでは、業者選定ミスによって引き起こされる典型的な失敗パターンを3つ紹介します。
・パターン1:丸投げ体制による品質崩壊(指示が末端まで届かない)
自社で職人を抱えず、受注した工事をそのまま下請けや個人の職人に丸投げしている業者に発注した場合、品質管理が極めて困難になります。元請け担当者様からの重要な指示(「ドレン周りは特に入念に」など)が、現場の末端で作業する職人まで正確に伝わらないことがあります。結果として施工不良が発生し、数年後の漏水トラブルに直結します。
・パターン2:技術力不足による漏水再発(原因特定ミス)
特に「雨漏りしているから直してほしい」という依頼の場合、問題が発生します。技術力の低い業者は、漏水箇所の上辺だけを補修しがちです。しかし、実際には水が躯体の想定外の場所を伝って浸入しているケースも多く、根本原因を特定しない限り漏水は再発します。原因究明を怠ったまま改修を進めることは、元請けにとって最大のリスクです。
・パターン3:アスベスト等の法令対応不備による工期完全ストップ
近年、アスベスト(石綿)に関する法令は急速に厳格化しています。防水改修においても、既存の防水材や下地調整材にアスベストが含まれている可能性は十分にあります。この事前調査や届出、適切な処理方法の選定を怠る業者を選んでしまうと、法令違反を指摘され、最悪の場合、工事の即時中断を命じられます。工期が完全にストップし、施主や近隣住民からの信用も失墜します。
■元請けの不安を解消する「本当に信頼できる」防水業者の3つの条件

では、これらの最悪の失敗を回避し、元請けとしてプロジェクトを成功に導くためには、どのような業者を「技術パートナー」として選ぶべきでしょうか。重要なのは以下の3つの条件です。
・条件1:「防水一級技能士」など、客観的な技術の証拠を持つ有資格者が在籍・管理しているか?
「技術力が高い」という言葉は曖昧です。その証拠となるのが、国家資格である「防水一級技能士」などの資格です。こうした有資格者が単に在籍しているだけでなく、現場の施工管理まで責任を持って担当しているかを確認すべきです。専門知識に基づいた確実な施工管理こそが、施工不良を防ぐ最大の防波堤となります。
・条件2:丸投げせず、「自社の熟練職人」による施工体制が確立されているか?
品質のブレを防ぎ、元請け担当者様の指示を現場の隅々まで行き届かせるためには、自社で熟練の職人を雇用・育成している業者が理想です。自社職人であれば、技術レベルが安定しているだけでなく、安全教育やマナー教育も徹底できます。急な工程変更などにも、会社として一体となって柔軟に対応できる体制は、元請けにとって大きな安心材料です。
・条件3:防水層だけでなく、外壁全体の劣化も診断できる「調査力」と「提案力」があるか?
漏水の原因は、必ずしも屋上やバルコニーの防水層だけとは限りません。外壁のひび割れ、シーリングの劣化、サッシ周りなど、複合的な要因が絡んでいることも多々あります。 そのため、単に防水工事を請け負うだけでなく、建物のどこに問題が潜んでいるのかを正確に診断できる「調査力」を持つ業者を選ぶことが重要です。防水だけでなく、外壁調査や補修工事にも対応できる総合的な知見があれば、漏水の根本原因を特定し、最適な改修提案が期待できます。
防水工事に関するご相談は、防水・シーリング工事のページをご覧ください。
■業者選定は、元請けの「未来の評価」を決める重要業務
大規模改修の防水業者選定は、単に工事を発注する「点」の業務ではありません。その選定結果が、数年後の建物の状態、施主様の満足度、ひいては元請けとしての自社の評価に直結する「線」の業務です。
目先の「価格」だけで選定するリスクと、長期的な安心感を買う「技術力(品質担保)」で選定するメリット。どちらが元請け担当者様の未来の評価を守ることにつながるかは、明らかでしょう。
プロジェクトの成功は、信頼できる技術パートナー選びにかかっています。まずは気になる業者が、どれだけ確実な施工体制を持ち、どれほどの技術者が在籍しているのか、具体的な事実を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
ご相談やご不明な点は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。