こんにちは。小平市で防水工事を手掛けるオーエス技研株式会社です。
管理しているビルやマンションの屋上で、風船のように膨らんだ箇所を見つけたことはありませんか?その「膨れ」、実は防水機能が低下している危険なサインかもしれません。放置すると大規模な雨漏りや建物の劣化に繋がる恐れも。この記事では、なぜ防水層が膨れるのか、その原因から正しい対処法、再発させないための工事のポイントまで、防水工事の専門家が分かりやすく解説します。
なぜ起こる?防水層が膨れるメカニズムと主な3つの原因
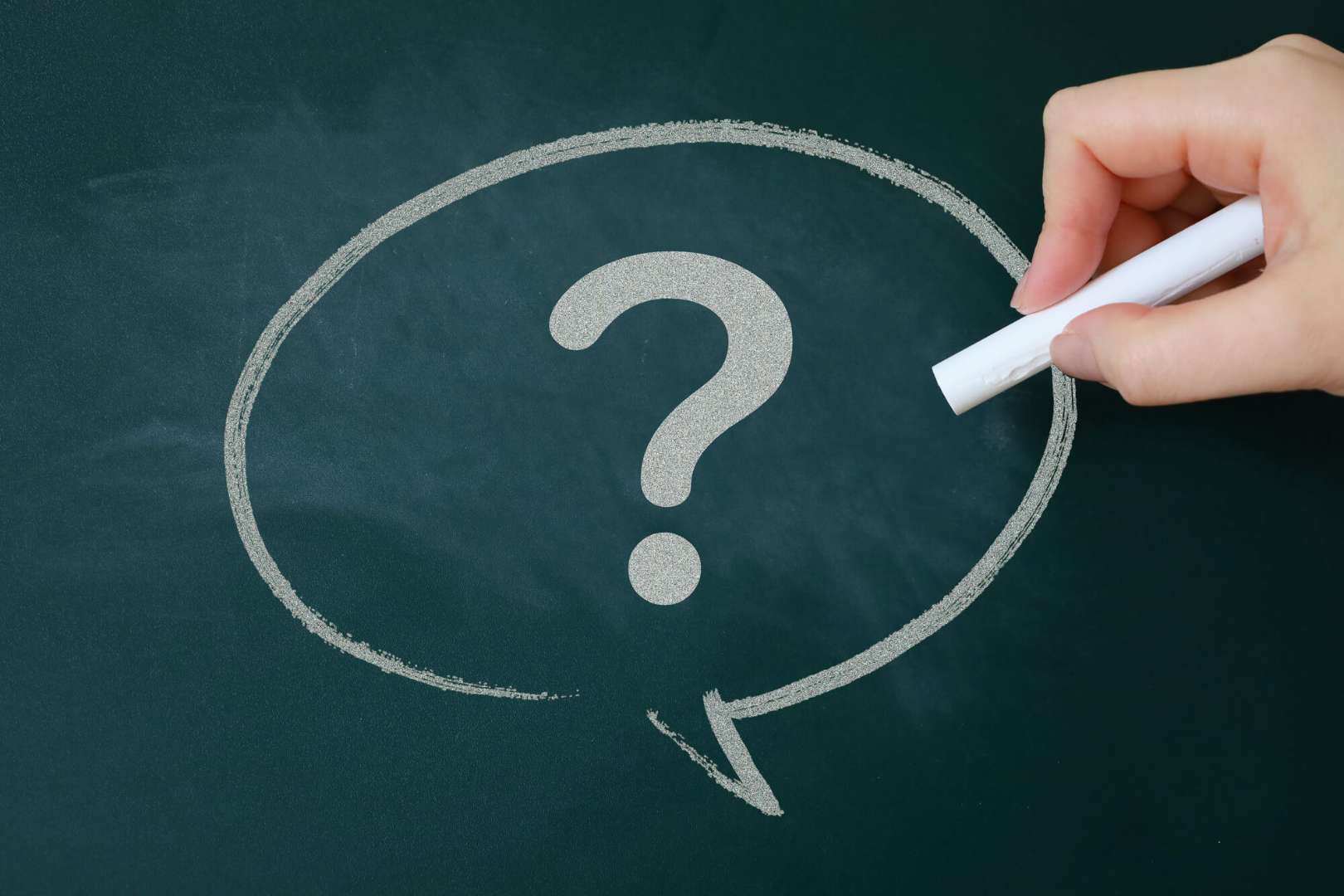
屋上の防水層に現れる風船のような「膨れ」。この現象は、防水層とその下のコンクリート下地との間に閉じ込められた「水分」や「空気」が、主な原因となって発生します。日中の太陽光によって屋上が熱せられると、閉じ込められた水分は水蒸気となり、空気は暖められて膨張します。この逃げ場を失った水蒸気や空気が防水層を内側から押し上げ、結果として「膨れ」を引き起こすのです。
特に、防水層にしっかりとした密着性が求められる「密着工法」で施工されている場合に発生しやすい症状です。では、なぜそもそも防水層の下に水分や空気が入り込んでしまうのでしょうか。その根本的な原因は、主に以下の3つが考えられます。
原因1:下地の水分・湿気
最も多い原因が、コンクリート下地自体に含まれている水分です。コンクリートは、施工時に多くの水分を含んでおり、完全に乾燥するまでには時間がかかります。もし下地の乾燥が不十分なまま上から防水層を被せてしまうと、内部に残った水分が年月を経て蒸発し、水蒸気となって膨れを発生させます。また、雨上がりの翌日など、下地が湿気を含んだ状態で施工した場合も同様のリスクを抱えることになります。
原因2:防水層の破断・劣化
長年の紫外線や風雨に晒されることで、防水層は少しずつ劣化していきます。すると、表面に目に見えないほどの小さな亀裂やピンホール(針で刺したような穴)が発生することがあります。そのわずかな隙間から雨水がじわじわと防水層の下に浸入し、溜まった水分が熱によって膨張することで膨れを引き起こします。最初は小さな膨れでも、放置すると水の浸入範囲が広がり、膨れも大きくなっていく傾向があります。
原因3:施工時の不備
残念ながら、新築時や前回の改修時の施工に問題があったケースも少なくありません。例えば、下地と防水層を接着させるプライマー(接着剤)の塗り忘れや塗りムラ、下地清掃の不足、規定の乾燥時間を守らないといった施工上の不備です。これらの問題があると、防水層が下地に正しく密着せず、隙間ができてしまいます。その隙間に空気が残ったり、後から水分が入り込んだりすることで、膨れの原因となります。
【工法別】こんな膨れは要注意!ウレタン防水とシート防水の違い

防水層の「膨れ」は、施工されている防水工事の種類によって、その現れ方に特徴があります。代表的な「ウレタン防水」と「シート防水」のケースを見ていきましょう。ご自身の建物の屋上がどちらのタイプか確認しながらご覧いただくと、より状況を理解しやすくなります。
ウレタン塗膜防水の場合:比較的小さな膨れが多発
液体状のウレタン樹脂を塗り重ねて防水層を形成するウレタン防水は、つなぎ目のないシームレスな仕上がりが特徴です。この工法での膨れは、比較的小さなものが点々と複数発生する傾向があります。これは、下地から発生した水蒸気が、塗膜の弱い部分を押し上げてできるためです。一つ一つは小さくても、広範囲に発生している場合は下地全体に湿気が多いサインと考えられます。
シート防水の場合:シート全体が大きく浮き上がる
塩化ビニルやゴム製のシートを貼り合わせて防水層を形成するのがシート防水です。この場合、シートの継ぎ目(ジョイント)の接着が甘くなったり、劣化して剥がれたりした箇所から水が浸入し、シートの下で大きく膨れることがあります。まるで防水シート全体がふんわりと浮き上がっているように見えるのが特徴で、強風でシートが飛ばされるリスクも考えられます。
防水層の膨れを放置するリスクと絶対にやってはいけないこと

小さな膨れだからと油断してはいけません。防水層の膨れは、放置すると深刻なトラブルに発展する可能性があります。膨れた部分は防水層が下地から剥がれている状態のため、非常に脆くなっています。歩行による摩擦や、飛来物によって簡単に破れてしまい、そこから大量の雨水が浸入してしまいます。結果として雨漏りを引き起こし、建物の構造自体を傷めることにもなりかねません。
自分で補修するのはNG!専門家による診断が必要です
膨れが気になって、「自分でカッターで切って空気を抜こう」「上からコーキング剤を塗って塞ごう」と考える方がいらっしゃいますが、それは絶対に避けてください。自己判断での補修は、かえって水の浸入口を広げてしまったり、一時的に塞いでも根本原因が解決しておらず、すぐに再発したりするケースがほとんどです。原因を正確に特定し、適切な処置を行うには、専門家による診断が不可欠です。
もう再発させない!「膨れ」に強い防水工事の2大ポイント

防水層の膨れの補修で最も大切なのは、「なぜ膨れたのか」という原因を突き止め、二度と再発させないための適切な工法を選ぶことです。そのために専門業者が採用する、信頼性の高い工事のポイントを2つご紹介します。
ポイント1:湿気を逃がす「脱気工法(通気緩衝工法)」
下地の水分が多い場合に特に有効なのが「脱気工法」です。これは、下地と防水層の間に意図的に空気の通り道を作り、発生した水蒸気を「脱気筒」という専用の排気口から外部へ逃がす仕組みです。これにより、水蒸気が防水層を押し上げるのを防ぎ、膨れの再発を根本から抑制します。この工法は専門的な知識と技術を要するため、業者選びのひとつの指標にもなります。
ポイント2:有資格者による正確な下地処理と施工管理
どんなに優れた工法や材料を選んでも、それを扱う職人の技術力が低ければ意味がありません。特に、下地の清掃や乾燥状態の見極め、適切なプライマーの選定といった下地処理は、防水層の寿命を決めると言っても過言ではないほど重要です。「一級防水施工技能士」のような国家資格を持つ職人は、これらの工程を正確に行う知識と経験を持っています。確かな品質を求めるなら、有資格者が在籍している専門業者に依頼するのが最も確実です。
防水層の膨れでお悩みなら、オーエス技研にご相談ください
ここまで解説してきたように、防水層の膨れは見た目以上に複雑な原因が絡み合っているケースが多く、その対処には専門的な診断力と技術力が不可欠です。
私たちオーエス技研には、国家資格である「一級防水施工技能士」が3名在籍しており、豊富な知識と経験に基づいて膨れの根本原因を徹底的に調査します。
公共工事も手掛ける高い技術力で、お客様の建物の状況やご予算に合わせた最適な補修・改修プランをご提案。「脱気工法」をはじめとする専門的な施工にももちろん対応可能です。小さな膨れ一つから、建物全体の防水改修まで、責任を持って対応させていただきます。
屋上防水の「膨れ」は、建物の寿命を縮める重大なサインです。原因を正しく突き止め、適切な処置を施すことで、雨漏りのリスクを回避し、建物の資産価値を守ることができます。自己判断で対処せず、まずは信頼できる専門家にご相談ください。
その「膨れ」、放置は危険です!専門家による無料診断・お見積りはこちら


